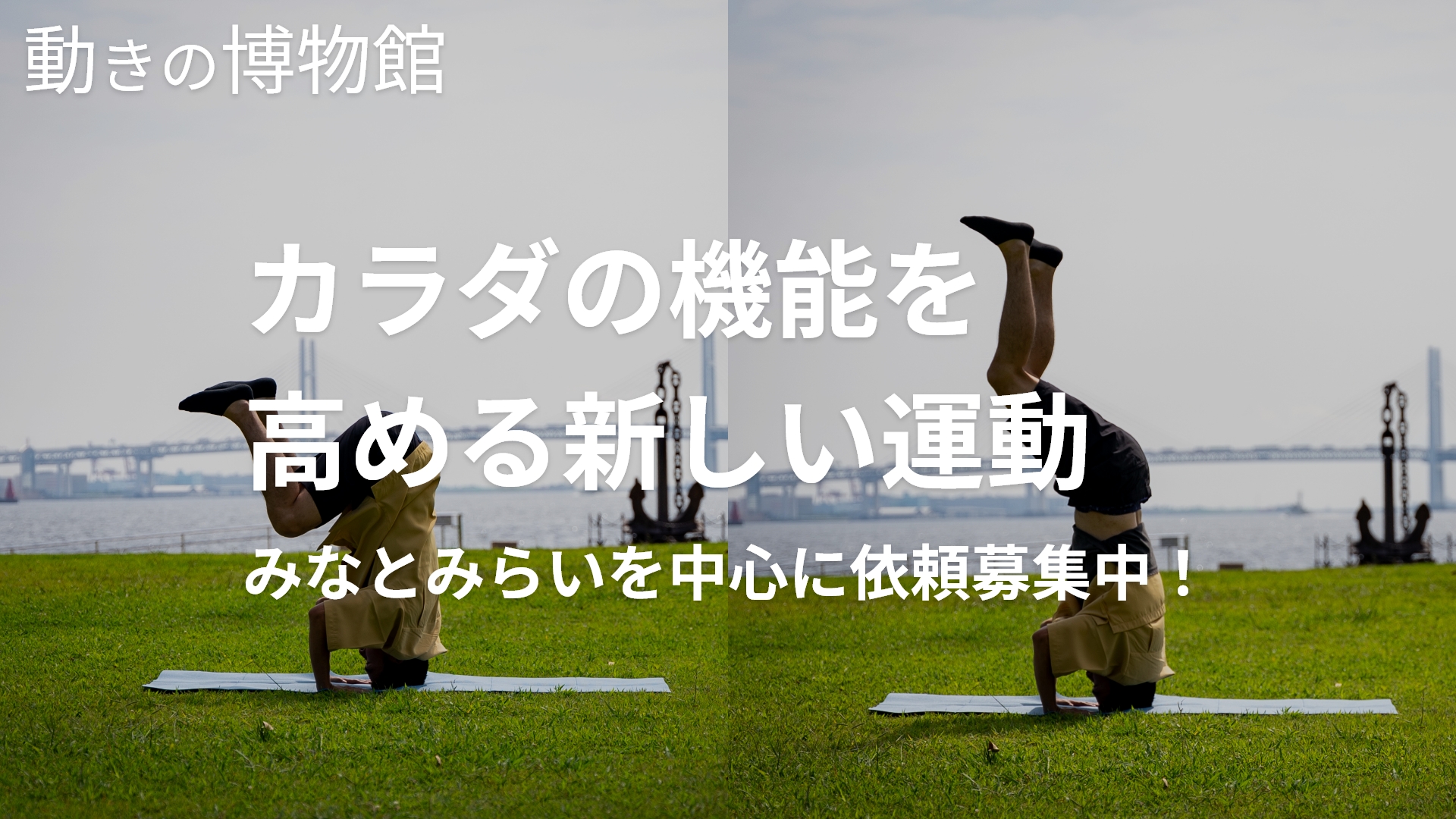このページでは、疲労について話していきたいと思う。
皆さんは、疲労という言葉を耳にした時に何を思い浮かべるだろうか?
疲労の種類
仕事や運動後の肉体的疲労、デスクワークやリモートワークによる目の疲れ眼精疲労、人間関係や将来の不安といった精神的な疲労、特に何もしていないけどスッキリしないような慢性疲労、最近よく耳にするようになったマインドフルネスという言葉、日本に昔からあった瞑想に海外のエビデンス・科学的根拠を付け足したようなものという解釈であっているだろうか?書店ではマインドフルネスや瞑想という題名の本が目につくことが以前に比べて、増えた気がする。情報社会の影響のためか、これは脳が疲れたと感じている人が増えたからではないだろうか。暴飲暴食をした翌日は、胃もたれや胸焼けを感じる人もいるだろう。これは内臓疲労にあたるだろう。この記事を執筆するにあたり内臓疲労という言葉をネット検索したところ、マラソン選手は大会後に内臓疲労になる例があるようだ。ゆっくり疲労について、考えてみると意外と興味深いものだ。他にも私は副腎疲労という言葉も耳にしたことがある。この言葉については、聞きなれない人も多いと思うので後ほど触れていきたいと思う。他にもここに挙げられていない疲労について思いつく方は是非私のYouTubeチャンネルにコメントを寄せていただきたい。






まとめると…
疲労の種類
- 肉体的疲労
- 眼精疲労
- 精神的な疲労
- 慢性疲労
- 脳の疲労
- 内臓疲労
- 副腎疲労
疲労とどう向き合うか
皆さんは、疲労とどう向き合っているか?
ここでは、疲労回復方法について考えていきたいと思う。
- 肉体的疲労
肉体的な疲労についてどんな対処の方法があるだろうか。マッサージ、半身浴、温泉、入浴剤、食事の管理、サプリメント、漢方薬、酸素カプセル、睡眠、栄養ドリンク、サウナ、鍼灸、ストレッチ、磁気パットやネックレス、例の如くやふってみると疲労回復ウェアなるものがあるというのだから驚きだ。 - 眼精疲労
眼精疲労について皆さんはどんな対処を行なっているだろうか。目を瞑る、スマホやPCの画面を見る時間を減らす、読書の時は部屋を明るくする、目薬、冷たいシートのようなものを目の上に置く、アイマスク、ツボを刺激する、ブルーライトカットのメガネをかける、ブルーベリーを食べる、ニンジンを食べる、森林を見る、こんなところだろうか。余談だが、フェルデンクライスメソッドを開発したモシェ・フェルデンクライスは興味深い発言をしている。まず、目を軽く閉じる。次に片手を両目の上に優しく被せる。こうすることで、光はさらに遮断されることになる。しばらく待つ。すると、人によっては完全な黒の世界でなくチカチカする部分があるとの事。これは、神経系統の疲労だとモシェ・フェルデンクライスは言っていました。部屋を暗くして仰向けになって行なってみること私はお勧めします。このことについて、アデレード大学で脳について研究している理学療法士が同僚に話したところ、半分くらいの人は何となく話を納得し、残りの半分の同僚は『ポカーン』としたようなのでこのホームページの読者の方は話半ばに聞いてほしい。仮に、私の話に興味を持ってくれた方の為に、あなたの目を閉じた世界にチカチカした部分があったとしたらその対処方法を伝えたいと思う。モシェ・フェルデンクライスは、人間の目が休まるのは黒の中に青が混じった色だと述べました。目を瞑ってチカチカする箇所に青みがかった黒を塗りつぶすのではなく、元から黒い部分を意識してそこを広げていくイメージでチカチカする場所が次第に薄れていくように想像してみてください。 - 精神的な疲労
どのような疲労にも似たような対処法があると思うので、それらは割愛しようと思う。心療内科など専門家に相談する、家族や友人に相談する、環境を変える、書籍からヒントを得る、ストレスを発散するこんなところだろうか。 - 慢性疲労・脳の疲労・内臓疲労
規則正しい生活、禅や、瞑想というワードを付け足すこともできるが疲労についての向き合い方は十分に話せたと思う。
副腎疲労について
副腎疲労については、各々ググって頂きたい。ぜひ、沢山ある情報から自分で内容を確認していただきたい。私の知っている医療機関では、看護師が副腎疲労のチェックシートを患者様に記入してもらい、対光反射をチェックして『どーん』あなたは副腎疲労です!!貴方には、このサプリが必要です。あなたにはこのボディーワークが必要です!!という光景が繰り広げられていた。例えば、疲労感が気になって来院してきた患者様に対応する場合は、副腎疲労というワードを使用するのも一つの手だと思う。ただ、私は疲労感で気になっている人に対しても、あえて副腎疲労と言わず、先に挙げた6つの疲労について取り扱っていきたいと思う。疲れやすい人は、そうでない人に比べ弱っている。そんな人に対して、副腎疲労という聞きなれない抽象的な言葉でカテゴライズして何になるのだろうか?たとえその人が副腎疲労症候群だとしても、より具体的な6つの疲労について着目し向き合えば自ずとよい方向に向かうと思う。
まとめ
皆さんがこのページを見て、少しでも疲労について関心が増えたり考えが深まったならば嬉しく思う。少なくとも、私の考える疲労については語ることができた。床ゴロ以外にも要因はあると思うが、私は以前出勤前後で懸垂を計10回✖️13セット行なっても、またそれまでできるようになる過程で一度も筋肉痛になりませんでした。それは、私はセルフケアとして床ゴロを取り入れていたからだと考えています。私は、床ゴロに出会う前は本当に練習しても懸垂ができないくらい運動音痴でした。床ゴロを通して疲労と上手く向き合えたこと、そして身体の使い方を学べた事が私が楽しく運動できた秘密だと思っています。