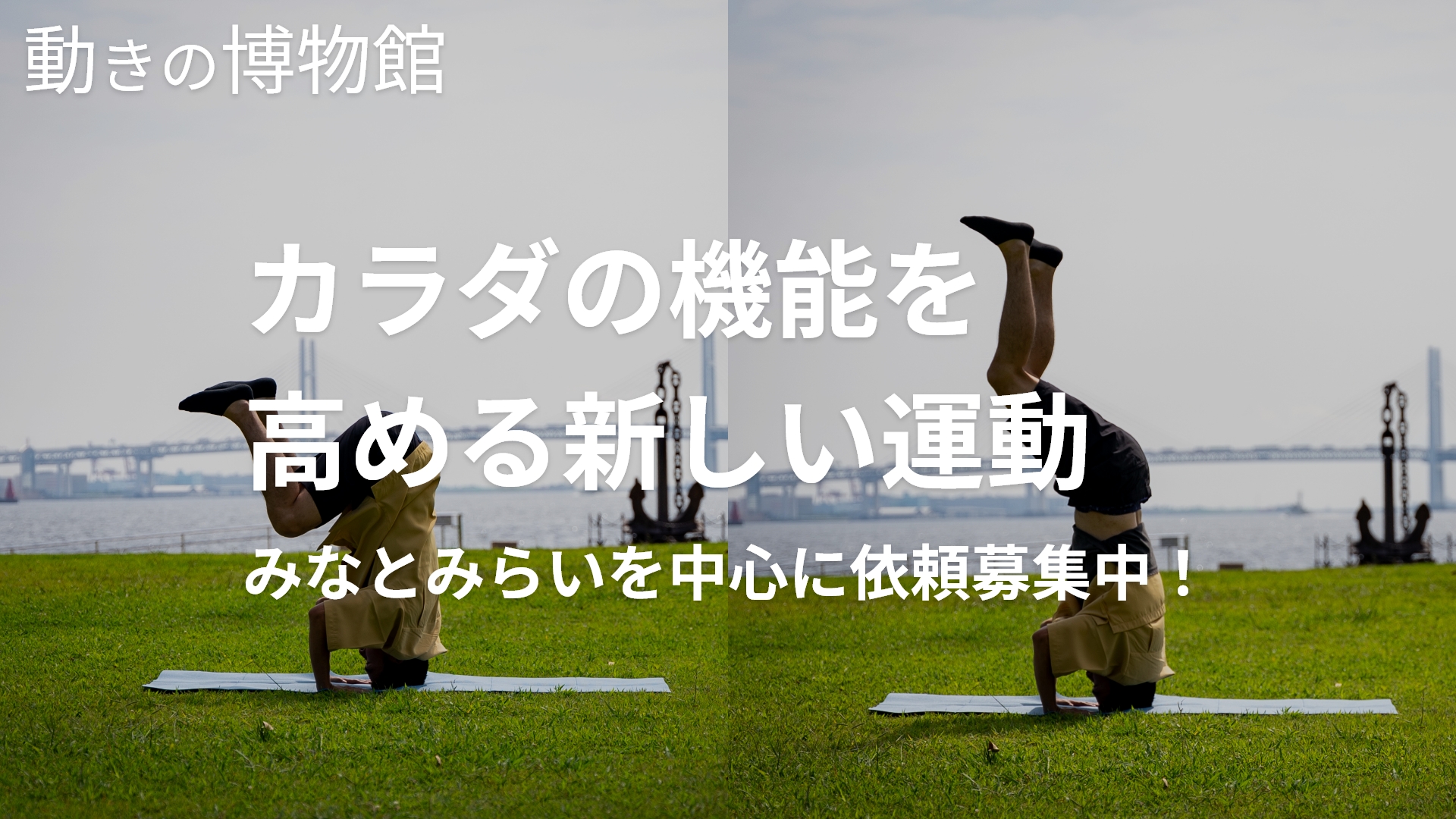不登校・頑張り屋さんなど(問題を抱えた方全般)
不登校の人にお勧め!!
この表現は思い切った表現である。これは、あくまで動きの博物館の個人的見解なので関心を寄せてくれた方がいたら全力でサポートする。まず、前提としてポリヴェーガル・理論という言葉は使わないでおく。5年以上前になるが私の周りにもポリヴェーガル・理論をもとにした運動療法をもとに例えば、東北大震災の津波を始めとする様々なトラウマやPDSDから救いたいと活動している医療従事者の方々がいました。また、その方々はジェモ・セラピーと言って植物の芽の成分を身体に取り入れると身体に良い、カシスの芽の成分はトラウマに効果的と言っていました。どちらも、私にはピンときません。動きの博物館では、自分の体験を通してオススメできると思ったことしかお勧めしません。ポリヴェーガル・理論を詳しく知りたい方は、各々勉強して頂きたいと思います。今から、私の認識するポリヴェーガル・理論を説明します。まず、自律神経には2種類あります。交感神経と副交感神経です。交感神経は活動的な時に働く神経でリラックスしている時に働く神経が副交感神経です。ポリヴェーガル理論では、副交感神経をさらに2種類に分けます。背側迷走神経と腹側迷走神経神経です。なぜ、二つに分けるのでしょうか?例えば、蛇が死んだふりをしてフリーズしたとしましょう。これは、リラックスしたというよりも身を固めている状態になります。つまり、副交感神経にもただ単にリラックス状態とそうじゃない状態に分けるという考え方です。私は、アデレード大学で脳について研究している人にフェルデンクライス・メソッドとポリヴェーガル理論についての研究があるか確認したところ、それについての研究はなされていないとのことでした。なので、私は抽象的な理論と切り離して動きの博物館をやっていきます。何故、動きの博物館は不登校の人にお勧めか?床ごろや楽ゴロは動きの選択肢を増やします。動きの選択肢を増やすことは、やがて行動の選択肢も増えます。つまり、問題を抱えた人は選択肢が減っている状態だと仮定すると、動きを通して行動の選択肢を増やしていこうという考えです。
細かく見てみると
- 不登校・引きこもり→学校に行かない・家にいるという選択肢しかない
- 自傷・自害 →そのような状態になった時に、他に選択肢がない
- 依存症 →そのような状態になった時に、他に選択肢がない
もちろん、どなたにもお勧め
動きの選択肢を増やすとは、どういうことだろうか?問題を抱えていないあなたも是非やってみよう。左へ後ろに振り返ってみましょう。もっと、振り返ってください。左に振り返るとき左の肩は後ろへ行き、右の肩は前に動いたと思います。左目は左に動き、頭も左に回ったと思います。おそらく、みなさん数ある動きの中から、その選択を選んだと思います。では次に、左へ後ろに振り返る時に、左肩を前へ右肩を後ろへ動かしてみましょう。これで、一つだけ動きの選択肢が増えましたね。これは、スポーツを行う上でも役立ちそうではありませんか?このような積み重ねが、やがて行動の選択肢も増えていくことを狙っています。数年前の研究で、スポーツ選手がゾーンに入っている間は交感神経と副交感神経が一対一で働いていると書いてあった気がします。動きの博物館で目指す動きは、常にリラックスしながらの動きなので、ある意味交感神経も副交感神経も同時に活性化していると言えるでしょう。
最後に
50年以上前の話なので、新聞に写真があまり載っていない英字新聞だったのかもしれませんが、選択肢が多いことについてのエピソードを紹介したいと思います。モシェ・フェルデンクライスは電車に乗っていました。隣の席に異国の人が腰掛けていました。その人は英字新聞を読んでいたのですが上下逆さまに新聞を持っていました。モシェは、それに気づいた時に異国人の自尊心を傷つけてしまわないように知らぬ顔をしていました。モシェの目的の駅はまだ先で、異国人も降りる気配がありませんでした。次第にモシェは指摘してあげないことがかわいそうだと考え始めました。勇気を出して、モシェは隣に座った新聞を上下逆さまに持って読んだふりをしている異国人に新聞が逆さまだと教えてあげました。すると、異国人の答えはこうでした。そんなのわかっている。私の街は貧しくて1冊の聖書を何十人も円になって囲って読んでいる。小さい頃から、そう読んでいるからどの方向からでも同じように読めるのです。これを聞いて、モシェは恥ずかしくなりました。文字が読めないと内心バカにしていた隣の男の方が、読む能力に優れていたのです。この男は、読むという行動において普通の人々よりも選択肢が多いことになります。